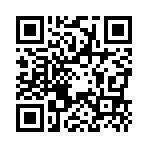2013年05月31日
小惑星1998QE2の観察
小惑星1998QE2(小惑星番号285263)は日本時間6月1日5時59分に地球に最接近した。アマチュアの観察には口径15cm以上の望遠鏡が必要(11~12等星)、最接近距離が月までの距離の15倍と遠く天球上の動きは遅いため望遠レンズ・望遠鏡での恒星追尾撮影で軌跡が露出時間を長くすると線状に伸びて写せそう。数分多カットを繋いだアニメも可能。梅雨でなかなか晴れ間が無いがまだ今週いっぱい観察可能です。

 図中の時刻は米国中部夏時間(ちゅうぶなつじかん、Central Daylight Time:略称CDT)です、時差を考慮する必要があり日本の方が、14時間進んでいます。
図中の時刻は米国中部夏時間(ちゅうぶなつじかん、Central Daylight Time:略称CDT)です、時差を考慮する必要があり日本の方が、14時間進んでいます。
米国からの観測画像多数→http://www.universetoday.com/102561/early-images-coming-in-of-asteroid-1998-qe2s-flyby/
http://www.planetary.org/blogs/emily-lakdawalla/2013/05301616-say-hi-to-asteroid-1998qe2.html
http://www.satflare.com/track.asp?q=A1998QE2#TOP
↓6月1日0:06(JST)薄い雲が通過する中なんとか姿を捉えた。
35mm版換算で焦点距離約500ミリのレンズ420秒間の動き。
6/3焦点距離約600ミリのレンズ120秒間の動き。
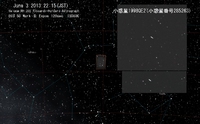


 図中の時刻は米国中部夏時間(ちゅうぶなつじかん、Central Daylight Time:略称CDT)です、時差を考慮する必要があり日本の方が、14時間進んでいます。
図中の時刻は米国中部夏時間(ちゅうぶなつじかん、Central Daylight Time:略称CDT)です、時差を考慮する必要があり日本の方が、14時間進んでいます。
米国からの観測画像多数→http://www.universetoday.com/102561/early-images-coming-in-of-asteroid-1998-qe2s-flyby/
http://www.planetary.org/blogs/emily-lakdawalla/2013/05301616-say-hi-to-asteroid-1998qe2.html
http://www.satflare.com/track.asp?q=A1998QE2#TOP
↓6月1日0:06(JST)薄い雲が通過する中なんとか姿を捉えた。
35mm版換算で焦点距離約500ミリのレンズ420秒間の動き。
6/3焦点距離約600ミリのレンズ120秒間の動き。

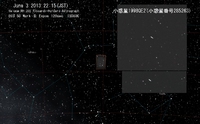
2013年05月11日
断層の露頭が気になって
下田市と南伊豆町の境に近い海岸線に盥岬歩道があり、此処に気になる地層露頭が有る。伊豆半島はこの春に国内ジオパークに認定されざっくり観光資源と注目しているが。それとは別に小生が単になぜ?とずっと以前から気になっていた場所だ。伊豆新聞に小山真人(静大)教授の「伊豆の台地の物語」連載が始まったことも有り2011年3月に撮影もしておいた場所なのだが注目されていない。高さ約15mの鏡面壁は地層萌えには(@_@;)と思うのですが。
 新聞の連載が進んで下田・南伊豆エリアに登場するかと待っていたが・・田牛の龍宮窟から弓ヶ浜に飛んでしまいがっかりした記憶がある。先生も伊豆の山中はくまなく巡られたそうだが松崎や南伊豆の海岸線には不踏地が在るとのこと納得です。そこで地質屋さんの巡検記録や断層マップやらいろいろ調べたが登場しません???見識ある方の見解を是非聞きたく思っております。コメント下記におよせ下さい。そこでとりあえず下の写真をみて皆様で判断しようではありませんか!
新聞の連載が進んで下田・南伊豆エリアに登場するかと待っていたが・・田牛の龍宮窟から弓ヶ浜に飛んでしまいがっかりした記憶がある。先生も伊豆の山中はくまなく巡られたそうだが松崎や南伊豆の海岸線には不踏地が在るとのこと納得です。そこで地質屋さんの巡検記録や断層マップやらいろいろ調べたが登場しません???見識ある方の見解を是非聞きたく思っております。コメント下記におよせ下さい。そこでとりあえず下の写真をみて皆様で判断しようではありませんか!

















 地質図を見ると此処に地質の境目があり不整合と一致する。断層?は古いほうの地層だ。私見をあえて述べさせていただくと繰り返す縞模様状の摩擦痕がポイントと思っています。断層には違いないが太古のプレートスロースリップが露頭となっているのでは!です。潮汐による風化浸食が進まないうちに調べていただきたい場所です。
地質図を見ると此処に地質の境目があり不整合と一致する。断層?は古いほうの地層だ。私見をあえて述べさせていただくと繰り返す縞模様状の摩擦痕がポイントと思っています。断層には違いないが太古のプレートスロースリップが露頭となっているのでは!です。潮汐による風化浸食が進まないうちに調べていただきたい場所です。
下田高校の有志是非研究対象にして文部科学大臣賞をゲットして下さい!!!例によって更に精細な画像がhttp://www.panoramio.com/photo/90115180にアップしてあります。一枚一枚ダウンロードに時間が掛りますが数ミリサイズまで解像した部分もあります。

 新聞の連載が進んで下田・南伊豆エリアに登場するかと待っていたが・・田牛の龍宮窟から弓ヶ浜に飛んでしまいがっかりした記憶がある。先生も伊豆の山中はくまなく巡られたそうだが松崎や南伊豆の海岸線には不踏地が在るとのこと納得です。そこで地質屋さんの巡検記録や断層マップやらいろいろ調べたが登場しません???見識ある方の見解を是非聞きたく思っております。コメント下記におよせ下さい。そこでとりあえず下の写真をみて皆様で判断しようではありませんか!
新聞の連載が進んで下田・南伊豆エリアに登場するかと待っていたが・・田牛の龍宮窟から弓ヶ浜に飛んでしまいがっかりした記憶がある。先生も伊豆の山中はくまなく巡られたそうだが松崎や南伊豆の海岸線には不踏地が在るとのこと納得です。そこで地質屋さんの巡検記録や断層マップやらいろいろ調べたが登場しません???見識ある方の見解を是非聞きたく思っております。コメント下記におよせ下さい。そこでとりあえず下の写真をみて皆様で判断しようではありませんか!下田高校の有志是非研究対象にして文部科学大臣賞をゲットして下さい!!!例によって更に精細な画像がhttp://www.panoramio.com/photo/90115180にアップしてあります。一枚一枚ダウンロードに時間が掛りますが数ミリサイズまで解像した部分もあります。
2013年05月07日
見るなら今でしょう
5月5・6・7日朝のみずがめ座η流星群はかつてないほど活発でした。01時台から経路の長い群流星が多発。平穏時の4~5倍の出現!
この流星群のもとは、かのハレー彗星。およそ3000年前に放たれたチリの帯が地球に接近し、流星が多くなる可能性が佐藤幹哉さんによって指摘されていました。凄いですね!
下記火球は静岡市清水区でも撮影されています離れた観測地での見え方の違いを確認してください。http://www.astroarts.jp/photo-gallery/photo/14087.html
同じ流星が見られる範囲http://studiolala.eshizuoka.jp/e965177.html

 きれいな夏の星座や天の川を見るのも5・6月のバンピーが静かに寝静まった夜半がベスト!誰かに見せたいかもしれないが心静かに独り占めがいい。気が向いたらカメラも向けては、最近のコンデジは良く写ります。フォーカスはマニュアルで一度遠くの明かりで無限大に合わせておきます。
きれいな夏の星座や天の川を見るのも5・6月のバンピーが静かに寝静まった夜半がベスト!誰かに見せたいかもしれないが心静かに独り占めがいい。気が向いたらカメラも向けては、最近のコンデジは良く写ります。フォーカスはマニュアルで一度遠くの明かりで無限大に合わせておきます。
この流星群のもとは、かのハレー彗星。およそ3000年前に放たれたチリの帯が地球に接近し、流星が多くなる可能性が佐藤幹哉さんによって指摘されていました。凄いですね!
下記火球は静岡市清水区でも撮影されています離れた観測地での見え方の違いを確認してください。http://www.astroarts.jp/photo-gallery/photo/14087.html
同じ流星が見られる範囲http://studiolala.eshizuoka.jp/e965177.html

2013年05月06日
手ごわい彗星撮影
5月満月を過ぎて月明かりの邪魔の無い時間に彗星を撮影する。 どの彗星も肉眼や小口径の望遠鏡では見えない。7等星から16等星と明るさに合わせて露出時間を変えている。
どの彗星も肉眼や小口径の望遠鏡では見えない。7等星から16等星と明るさに合わせて露出時間を変えている。 地球ー太陽間の距離程も離れているが焦点距離1,200mmとなると地球の自転による星の動きに彗星の動きが加わり難しい撮影となる。それぞれ条件の良い高度に昇る合間に子持ち銀河や球状星団を撮影する。今年の秋から暮に大彗星となると期待しているアイソンは火星の軌道のまだ外側で地球の公転も太陽を挟んで逃げる方向になり光度はなかなか増してこない。そろそろ太陽の後ろ側に回ってしまい、8月下旬に明け方の空に見えだすまでしばしのお別れとなる。
地球ー太陽間の距離程も離れているが焦点距離1,200mmとなると地球の自転による星の動きに彗星の動きが加わり難しい撮影となる。それぞれ条件の良い高度に昇る合間に子持ち銀河や球状星団を撮影する。今年の秋から暮に大彗星となると期待しているアイソンは火星の軌道のまだ外側で地球の公転も太陽を挟んで逃げる方向になり光度はなかなか増してこない。そろそろ太陽の後ろ側に回ってしまい、8月下旬に明け方の空に見えだすまでしばしのお別れとなる。
 どの彗星も肉眼や小口径の望遠鏡では見えない。7等星から16等星と明るさに合わせて露出時間を変えている。
どの彗星も肉眼や小口径の望遠鏡では見えない。7等星から16等星と明るさに合わせて露出時間を変えている。 地球ー太陽間の距離程も離れているが焦点距離1,200mmとなると地球の自転による星の動きに彗星の動きが加わり難しい撮影となる。それぞれ条件の良い高度に昇る合間に子持ち銀河や球状星団を撮影する。今年の秋から暮に大彗星となると期待しているアイソンは火星の軌道のまだ外側で地球の公転も太陽を挟んで逃げる方向になり光度はなかなか増してこない。そろそろ太陽の後ろ側に回ってしまい、8月下旬に明け方の空に見えだすまでしばしのお別れとなる。
地球ー太陽間の距離程も離れているが焦点距離1,200mmとなると地球の自転による星の動きに彗星の動きが加わり難しい撮影となる。それぞれ条件の良い高度に昇る合間に子持ち銀河や球状星団を撮影する。今年の秋から暮に大彗星となると期待しているアイソンは火星の軌道のまだ外側で地球の公転も太陽を挟んで逃げる方向になり光度はなかなか増してこない。そろそろ太陽の後ろ側に回ってしまい、8月下旬に明け方の空に見えだすまでしばしのお別れとなる。